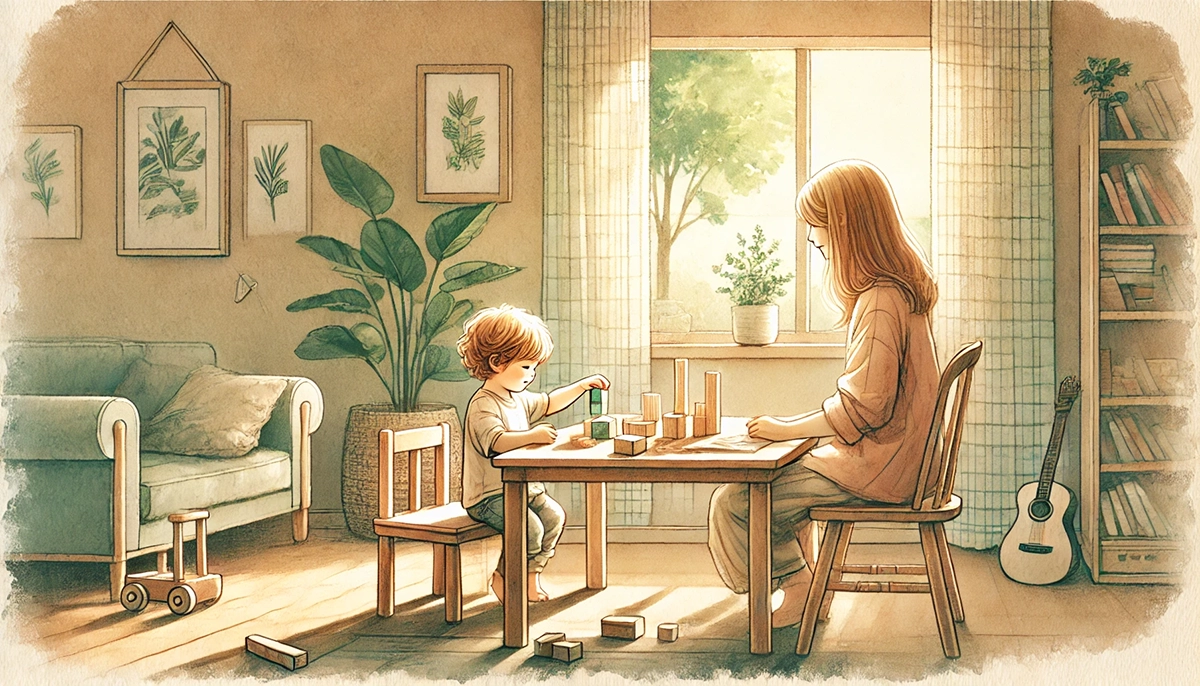「ママ、これどうすればいいの?」「やってー!」
そんな子どもの声に、毎日バタバタと応えていませんか?
もちろん、子どもを手助けしたくなる気持ちは自然なこと。でも実は、「あえて手を出さない」ことが、子どもの自立心と生きる力を育てるうえでとても大切なんです。
今回は、イタリア発の教育法「モンテッソーリ教育」から学ぶ、子どもの能力を引き出す関わり方についてご紹介します。
「できるからやる」じゃない。「やってみたい」がすべてのはじまり
モンテッソーリ教育では、子どもは「自ら育つ力を持っている存在」とされています。
「親がやらせる」のではなく、子ども自身が「やりたいからやる」――この姿勢を大切にしているのです。
たとえばこんな場面、どうしますか?
- 子どもが服をうまくたためない
- ボタンをうまく留められずにイライラしている
- おもちゃを片づけるのに時間がかかっている
つい手を出したくなりますよね。でも、そこを「見守る」ことが大切。
失敗しても、試行錯誤しても、「自分でできた!」という達成感が、次のチャレンジへとつながるのです。
NGな関わり方とOKな関わり方
| NGな関わり方 | OKな関わり方 |
|---|---|
| わからないことをすぐに教えてしまう | 「どうしたらできるかな?」と一緒に考える |
| なんでもママがやってしまう | 手出しせず、でもそっと見守る |
| 子どもの行動を先回りしてしまう | 失敗も経験として受け入れる |
「決める力」が育つと、子育てが楽になる!
日常の小さな選択も、子どもに任せてみましょう。
- 「今日はどの服を着たい?」
- 「どのお皿で食べたい?」
- 「先にお風呂に入る?ごはんにする?」
大人にとっては些細なことでも、子どもにとっては「自分で選ぶ」練習になります。
選ぶことで責任感が芽生え、「やらされる」から「やる」に変わるのです。
これができるようになると、親のイライラが減って、子育てがぐっとラクになりますよ。
「待つ勇気」がママを変える
子どもが何かに挑戦しているとき、すぐに手助けするのではなく、「できるかもしれない」という目で見守ってあげましょう。
子どもにとっての成長のチャンスは、親にとっての「待つ力」の訓練でもあります。
見守ることは放置ではありません。信じて、任せることなのです。

実際のママの声
「お手本を見せても全然やらない。つい怒ってしまう…」
そんなときは、“もう一度だけ見せて、あとは待つ”を意識してみてください。
子どもは「やらされる」よりも、「見て覚えて、自分でやる」方が身につきやすいんです。
見守られた子は、自分で人生を選べる子に育つ
この時期に「自分で選び、自分で決める」経験を積んだ子は、
やがて自立した大人になります。
「これでいいのかな?」と迷ったとき、答えを外に求めず、自分の中の声を聞ける人になるのです。
おわりに:子どもはママの「お世話をする対象」ではない
「ちゃんとやらせなきゃ」「失敗させたくない」
そんな気持ちを少しだけ横に置いて、「この子はできる子」と信じてみてください。
子どもは、ママが思う以上にすごい力を秘めています。
その力を引き出せるのは、他でもない、ママの“見守る力”です。

【参考文献】
『見守られた子は伸びる!自分の頭で考え、自分で人生を選択できる子になる』より抜粋(モンテッソーリ教育をベースにした子育て実践ガイド)