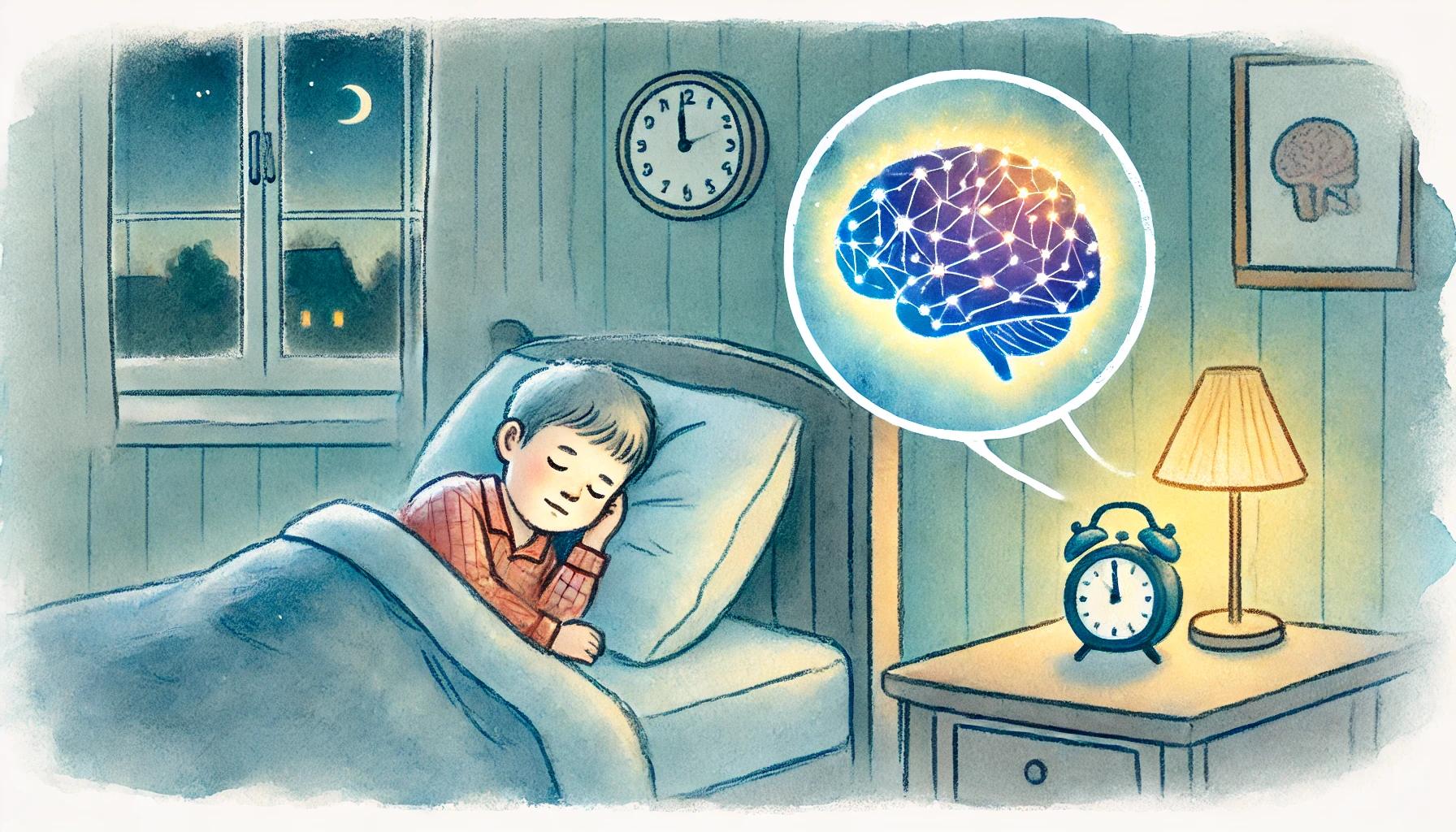子育てママなら子どもの成長と健康を何よりも願いますよね。ところが、普段何気なく食卓に並ぶ食品に含まれる合成着色料が、子どもの発達に影響を与える可能性が指摘されています。
合成着色料とは?
合成着色料とは、食品をきれいな色に見せるために人工的に作られた色素のことで、主に石油由来の「タール系色素」が使用されています。例えば、お弁当のお漬物やお菓子など身近な食品に多く含まれています。

子どもの発達障害との関連
近年、特に問題視されているのが「黄色4号」「黄色5号」「赤色40号」「赤色102号」といった合成着色料です。これらの添加物が子どもの集中力低下や多動傾向(ADHDの症状)の一因になるという報告が海外でなされており、イギリスではこうした注意喚起が製品パッケージにも明記されています。
一方で、日本国内ではそのような表示義務がなく、多くの消費者が知らないうちにこれらの添加物を摂取している状況です。
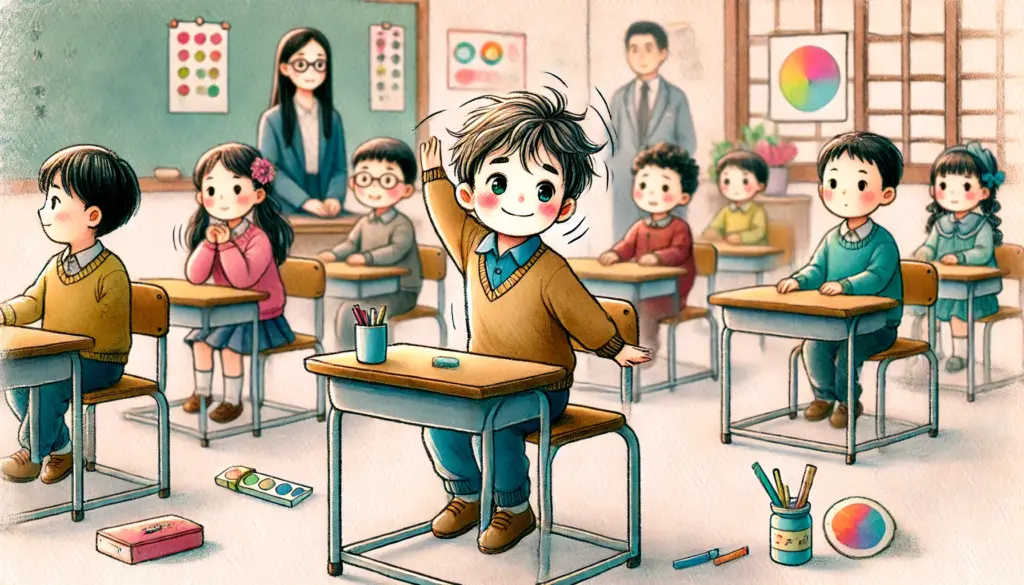
なぜ日本では規制が甘いのか?
日本人の食文化は「美しさ」にこだわりが強く、見た目が鮮やかで均一な食品を好む傾向があります。この消費者のニーズに応える形で、メーカーも着色料を多用しているのです。
また、EUやアメリカでは使用が禁止または厳しく規制されている着色料も、日本では一部規制が甘く、子ども向けのお菓子や食品に広く使われている現状があります。
ママができること
子ども自身は食べる食品を自由に選べないため、ママの選択が子どもの健康や発達に大きく影響します。
大切な子どもを守るために、次のことを心がけましょう。
- 食品表示をしっかり確認する。
- 「赤色〇号」「黄色〇号」など、合成着色料が記載されている食品を避ける。
- 自然な食材を選ぶ。
- お菓子や加工食品の購入を控え、手作りを取り入れる。
- 食品添加物に関する正しい情報を知り、周囲にも伝える。
毎日の小さな選択が、子どもの未来を守ります。家族の健康を守るために、ぜひ食品添加物について一緒に考えてみましょう。

【参考文献】
- 加工食品診断士養成講座テキスト第1回(安部氏による食品添加物に関する講義)