「うちの子、本は好きだけど、国語の成績がイマイチで…」
そんな悩みを持つママは少なくありません。
実は、読書好き=国語が得意ではないんです。
文章を深く理解し、感情や論理をしっかりとつかむには、“音読”の習慣がカギになります。
音読が育てる“5つの力”
音読はただの読み上げではありません。
毎日続けることで、子どもにこんな力が身につきます。
1. 語彙力と文法感覚:「を」「に」「から」など助詞の使い方が自然に身につく
2. 読解力:黙読ではスルーしがちな細かい描写も、声に出すことで理解が深まる
3. 集中力と視野の広さ:読みながら先を目で追うことで、周辺視野が鍛えられる
4. 論理的思考力:説明文の筋道や構成を音で把握できるようになる
5. 感情の理解:抑揚をつけて読むことで、登場人物の気持ちにも寄り添える

「読書好き」なのに国語が苦手な理由
「本はよく読むのに、成績が伸びないんです…」
それは、“飛ばし読み”や“ストーリー追い”が習慣化しているからかもしれません。
• あらすじだけを把握して満足してしまう
• 説明文や情景描写をすっ飛ばしてしまう
• 心理描写を読み取る力が育っていない
そんな子には、「一部を音読させてみる」ことが効果的です。
黙読では気づけなかった大切な部分に、声に出すことで出会えるからです。
算数も得意になる!?音読と「3行の壁」
文章問題になると「急に解けない」と感じる子、いませんか?
これも実は、読解力不足が原因です。
音読の習慣がある子は、いわゆる「3行の壁(長文への苦手意識)」を軽々と超えられます。
「この問題わからない」と言っていた子も、音読させると「あ、わかった!」と突然解き始めることもよくあります。
効果的な音読法|「通常の音読」と「速音読」を組み合わせる
音読には2つの種類があります。
• 通常の音読:感情を込めて、抑揚をつけて読む。童話や物語におすすめ。
• 速音読:できるだけ速く、はきはきと。説明文や科学系読物におすすめ。
この両方を取り入れることで、感情の理解と論理の把握、どちらも鍛えられます。
音読は何歳から?どんな本を選べばいい?
• 小学1年生からスタートを
• 読む本は、子どもが「ちょっと面白い」と思えるものを
• 説明文なら【小学生新聞】【科学絵本】【ジュニア新書】などもおすすめ
子どもが興味をもつ分野の本を、少し難しくても選んでみてください。
お母さんが聞き役になることで、親子のコミュニケーションも深まります。
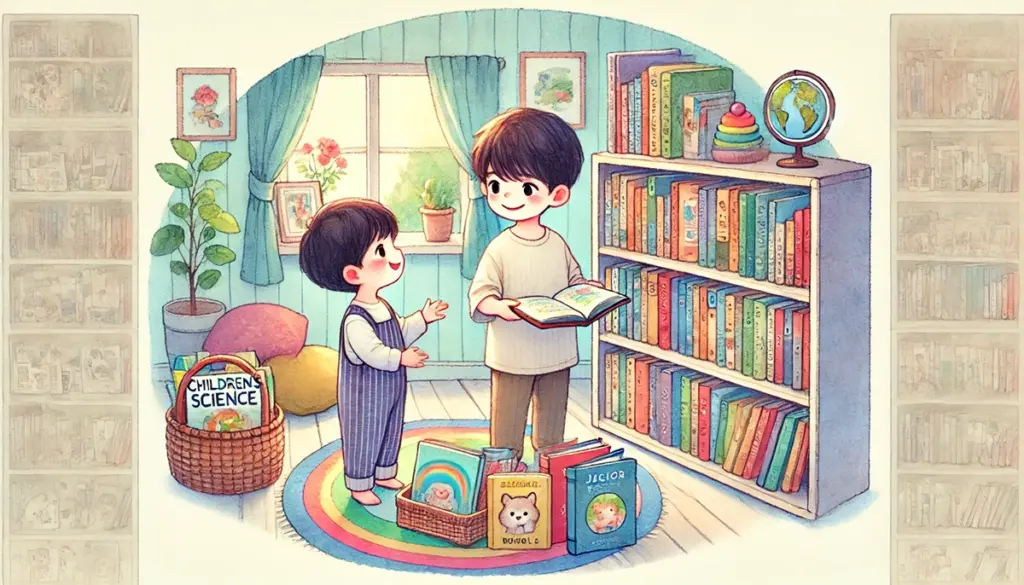
音読の“前段階”は読み聞かせ
読み聞かせをたくさんしてもらった子は、自然と本が好きになります。
そして、自分で読む=音読、も楽しくできるようになります。
中学年以降は、お母さんが読みたい本を音読してもらうのもおすすめです。
「ママのために読んであげるよ」といった関係が、子どもの自己肯定感も育ててくれます。
まとめ|「音読」が学力も心も伸ばしてくれる!
音読は、子どもの言葉の力、考える力、感じる力すべてを育てる最強の習慣です。
毎日5分でも、まずは教科書や好きな本からスタートしてみましょう。
音読を習慣にするだけで、子どもの未来が大きく変わります。

【参考文献】
• 『声に出して読みたい日本語』(齋藤孝/草思社)
• 『子どもに「勉強しなさい」と言わずにすむ方法』(親野智可等/主婦と生活社)
• 『学力の経済学』(中室牧子/ディスカヴァー・トゥエンティワン)
• 教育関係者・学習塾講師による解説記事



