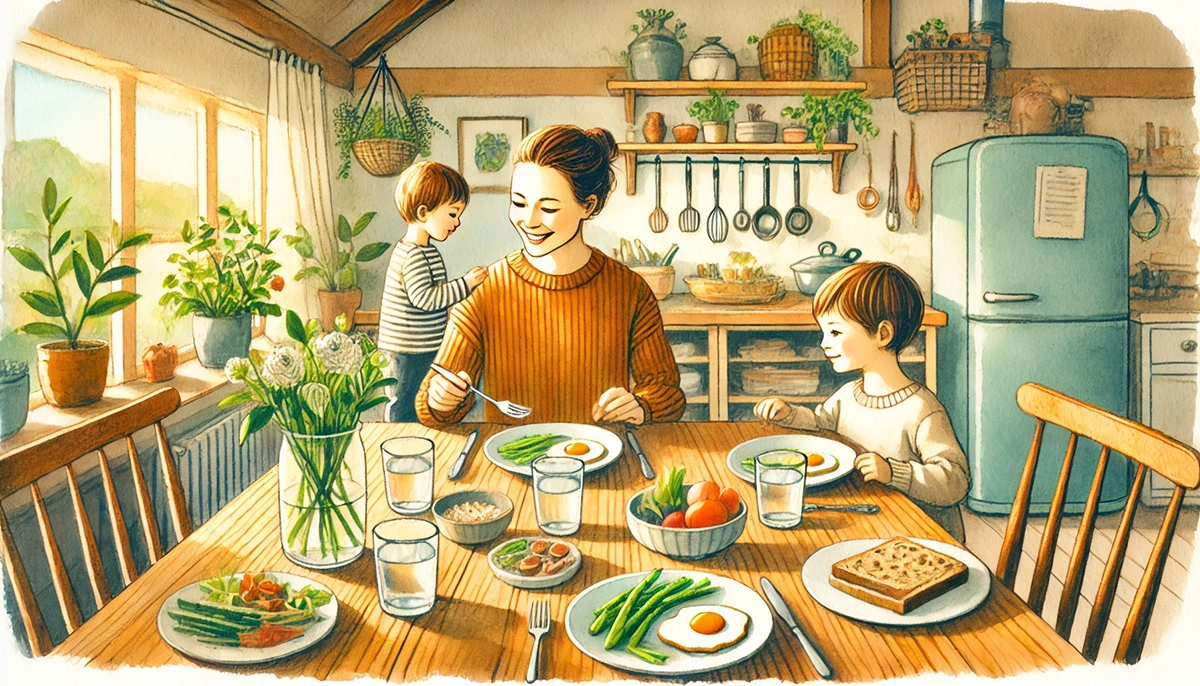「このお肉、まだ大丈夫かな?」
「このパック、昨日と同じ商品に見えるけど…?」
スーパーで毎日たくさんの食材を目にするママたち。
でも、“賞味期限”や“消費期限”の本当の意味を知っている人は意外と少ないかもしれません。
今回は、「スーパー 賞味期限 裏側」「巻き直し 食品業界 リスク」といった、食品表示の現実と安全な見極めポイントをお届けします。
賞味期限と消費期限の違い、正しく知ってる?
まず、よく混同されるこの2つ。
- 賞味期限…「おいしく食べられる期限」(おおむね5日以上日持ちするもの)
- 消費期限…「安全に食べられる期限」(おおむね5日以内に傷むもの)
賞味期限は多少過ぎてもすぐに悪くなるわけではありません。
一方で消費期限が過ぎた食品は、食中毒のリスクがあるので注意が必要です。
業界のリアル「巻き直し」って?
スーパーでは、期限切れ直前の商品に新しいラベルを貼り直して再販売する行為が、一部で行われています。これを業界用語で「巻き直し」と呼びます。
- ラベルを貼り直す
- ラップを巻き替える
- あたかも“新しい商品”に見せる
これ自体は違法ではなく、法律の隙間を利用している状態。
なぜなら、消費・賞味期限を途中で変更しても、それを明確に禁止する法律は存在しないからです。

「製造日」は“いつ”なのか?
食品衛生法では、「製造日」は最終加工日とされています。
でも、その定義はあいまいで、たとえば…
- 冷凍肉を解凍した日
- パックにラップした日
これらを業者が自由に「製造日」として記載できるのが現状です。
つまり、「今日製造」とあっても、実際は数日前に加工された食材の可能性もあるのです。
表示されない原材料もある
たとえば、スーパーのお惣菜コーナーで買える対面販売のお弁当や刺身のパック。
実は、これらには原材料や添加物の表示義務がない場合もあります。
なぜなら、
「対面販売では店員がすべての情報を把握していて、説明できるから表示義務は必要ない」
とされているからです。
でも、忙しい時間帯にひとつひとつ質問するのは現実的ではないですよね。

廃棄を避けるための“再加工”も…
賞味期限が近づいた食材は、さらに加工品に姿を変えて売られることもあります。
例:鶏もも肉 → 味付け焼肉用 → 唐揚げ → 唐揚げ弁当
一見わかりませんが、何段階も加工されるうちに、もとの鮮度や日付が見えなくなるのです。
食品ロス削減の「3分の1ルール」って?
スーパーでは、食品の納入と販売に「3分の1ルール」が適用されています。
- 賞味期限の3分の1までに納入
- 3分の2までに販売
- 残りの1分の3で値引き・廃棄
期限が近い商品が店頭に並ぶこともあると知っていれば、必要な分を計画的に買って食品ロスを防ぐことができます。
ママにできる食品選びの工夫
家族の健康を守るママだからこそ、できることがあります。
- 期限ギリギリの商品は“加工品”を疑う
- “当日製造”の意味を鵜呑みにしない
- 対面販売の惣菜や刺身は信頼できる店舗で
- 「賞味期限が近い=悪い」ではなく、自分の目で確認
まとめ|知って選ぶことが“家族を守る力”になる
スーパーでの買い物は、ただ安さや便利さだけで決めてはいけない時代になってきています。
賞味期限やラベルの裏側には、見えない工夫や事情、そして時にはリスクも潜んでいます。
だからこそ、「知って選ぶ」ことが、家族の健康を守る第一歩なのです。

【参考文献】
- 農林水産省「賞味期限と消費期限の違い」
- 消費者庁「食品表示基準について」
- NHKクローズアップ現代「食品表示の見えない落とし穴」
- フードロス削減推進法関連資料(消費者庁)
- 食品ロス・賞味期限と業界慣習に関する解説記事(日本食品新聞)