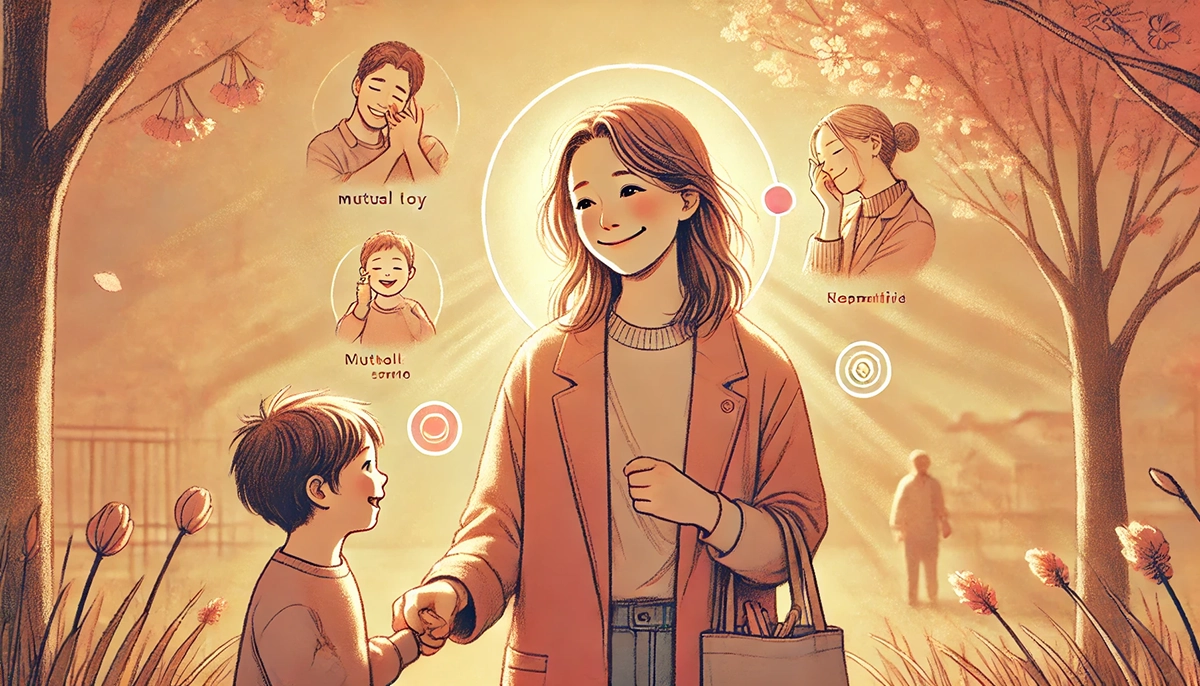最近、お子さんがこんな様子はありませんか?
- すぐ疲れてしまう
- イライラしやすい
- 集中できない
- 頭が痛い、眠れない
まるで大人のような不調。でも実はこれ、小学校高学年以降の子どもに増えている“自律神経の乱れ”によるサインかもしれません。
子どももストレス社会を生きている
勉強、塾、習いごと、友だち関係…。現代の子どもたちは毎日が忙しく、時間に追われています。
その中で、食事や睡眠のリズムが乱れやすくなり、自律神経の働きがうまくいかなくなることがあるのです。
自律神経とは、体を「活動モード」にする交感神経と、「休息モード」にする副交感神経がバランスをとりながら体の状態を保つ仕組み。このバランスが崩れると、疲れやすさや情緒不安定といった症状が現れやすくなります。
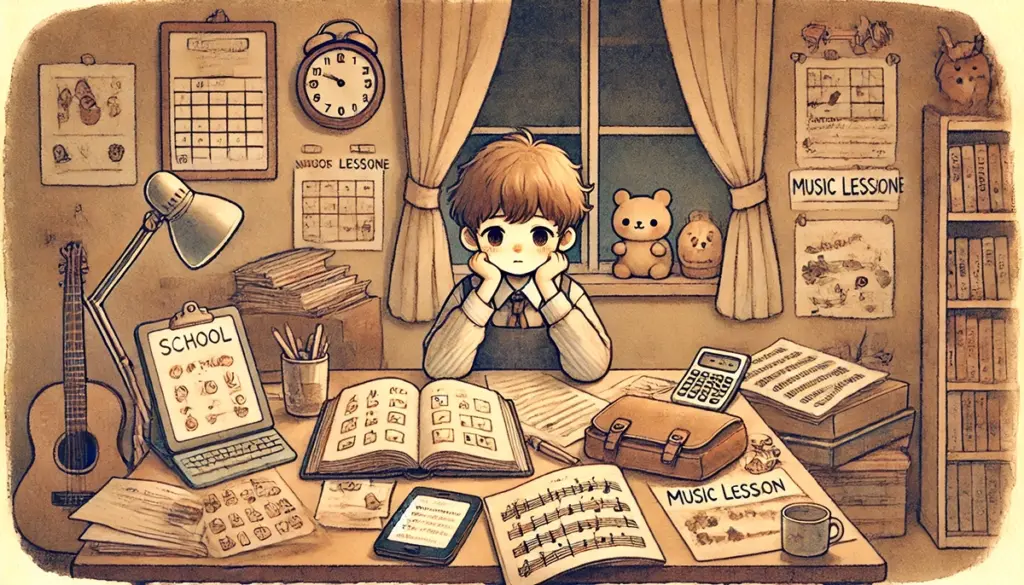
「やる気」のもとは食事にあり!
特に大事なのが、たんぱく質。
肉、魚、卵、乳製品、大豆などに含まれる「必須アミノ酸」は、脳内の神経伝達物質であるセロトニンやドーパミンの材料になります。
- セロトニン:気持ちを安定させ、夜の「眠りホルモン(メラトニン)」の材料にも
- ドーパミン:やる気や集中力を高める
つまり、たんぱく質が不足すると、やる気も睡眠もダウンしてしまうのです。
食事タイミングも大切
塾などで夕食が遅くなるお子さんには、夕方に軽く補食を。帰宅後の食事は、豆腐の雑炊や卵スープなど消化の良いものがおすすめ。
胃を休めることで、夜もぐっすり眠れて、翌朝しっかり朝ごはんが食べられます。
今日からできる!自律神経を整える4つの習慣
- たんぱく質をしっかりとる
肉・魚・卵・大豆などを意識的にとりましょう。 - 朝日を浴びる
朝日を浴びると、セロトニンが分泌され、心が安定します。 - 夜は照明をオレンジ系に
蛍光灯やスマホのブルーライトはメラトニンの分泌を妨げます。夜は間接照明や電球色のライトにしてみて。 - リズム運動を取り入れる
ラジオ体操やウォーキングなど、10〜30分の軽い運動も効果的です。
忙しい毎日の中でも、ちょっとした工夫で子どもの不調はグッと軽くなります。
食事・光・運動といった「生活のリズム」を整えることが、自律神経の安定につながるのです。
「なんだか最近調子が悪そう…」と感じたら、まずはたんぱく質と生活リズムを見直してみてくださいね。

【参考文献】
- 『自律神経の整え方』 日本自律神経学会
- 厚生労働省「子どもの食生活指針」
- 一般社団法人 日本臨床栄養協会「たんぱく質とアミノ酸の基礎知識」
- Sleep Foundation「光と睡眠の関係」
- 文部科学省「子どもと運動の関係」