〜怒る前に知っておきたい、ママのための心のスイッチ〜
「どうしてこんなことするの!」「何度言ったらわかるの!」
つい怒ってしまったあと、自己嫌悪に陥ることはありませんか?
子どもをしっかり育てたい、ちゃんとした人になってほしい――
そんな思いから出る「叱る」という行動。でもその“叱り方”、実は逆効果になっている可能性があるんです。
今回は「叱る」という行為の本質と、叱らずに子どもを導く3つの工夫をご紹介します。
叱ることで、本当に子どもは変わるの?
「叱ればわかってくれる」――そう思っていませんか?
でも実際には、叱られたときの脳は“学べない状態”にあるのです。
叱られた子どもの心の中には、「怖い」「不安」「早く終わってほしい」などのネガティブな感情が広がります。
その結果、脳は“戦うか逃げるか”のモード(=ストレス反応)に入り、思考力や判断力が大きく低下します。
これは、動物が危険を察知したときと同じ反応です。
本能的に「戦う」か「逃げる」かを即決するため、脳はじっくり考える機能をシャットダウンしてしまうのです。
たとえ「ごめんなさい」と口にしていても、それは納得しているわけではなく、その場を逃れたいだけの反応であることも少なくありません。
なぜ、私たちは叱ってしまうの?
大きく分けて2つの理由があります。
①「苦しまないと変わらない」という思い込み
叱ることで行動が変わった経験があると、「叱るのは効果的」と思い込んでしまいます。
でもそれは、子どもが「恐怖」で行動を止めただけで、心の中で納得しているわけではありません。
② 叱ることで“気持ちよさ”を感じる
相手をコントロールできたと感じると、人は気持ちよくなります。
実は「叱る」という行為そのものが、知らず知らずのうちに快感になり、習慣化してしまうこともあるのです。

子どもとの関係が変わる!叱らないための3つの工夫
1. 【自分の“当たり前”を見直す】
「食事は全部残さず食べるべき」「おもちゃはすぐ片づける」
――それって、本当に子どもにとっても正しい“常識”でしょうか?
私たちが「当然」と思っていることも、他の人や時代、状況によって変わるもの。
叱る前に、自分の“当たり前”が今の子どもにも本当に合っているのか、一度立ち止まって考えてみましょう。
2. 【あらかじめ伝えておく】
何かが起きてから叱るのではなく、前もって伝えておくことが大切です。
たとえば図書館に行く前に、「ここでは静かにしようね」と一言添えておくだけで、子どもも心の準備ができます。
冷静な状態での説明は、怒られて受ける言葉よりずっと心に届きます。
3. 【どうしても叱るなら、短く】
命の危険がある時などは、注意する必要があります。
そんな時は、「危ない!」など一言で十分です。
その後は、優しくフォローしながら、どうすればよかったかを一緒に考えましょう。
長々と叱ると、ストレスだけが残ってしまいます。
子どもは「自分で気づいた時」にしか成長しない
どれだけ教えても、どれだけ怒っても、本当に子どもが変わるのは「自分で気づいた時」です。
自分で決めたことは、やる気も責任感も段違い。
失敗も、誰かに言われたのではなく、自分で気づくからこそ学びにつながります。
おわりに:叱らないママになろうとしなくていい
完璧なママでいようとしなくて大丈夫。
怒ってしまう日があっても、「次はどう伝えようか」を考えることが前進です。
叱らなくても、子どもと信頼でつながる関係はつくれます。
あなたのその一歩が、子どもの未来にやさしく届くはずです。
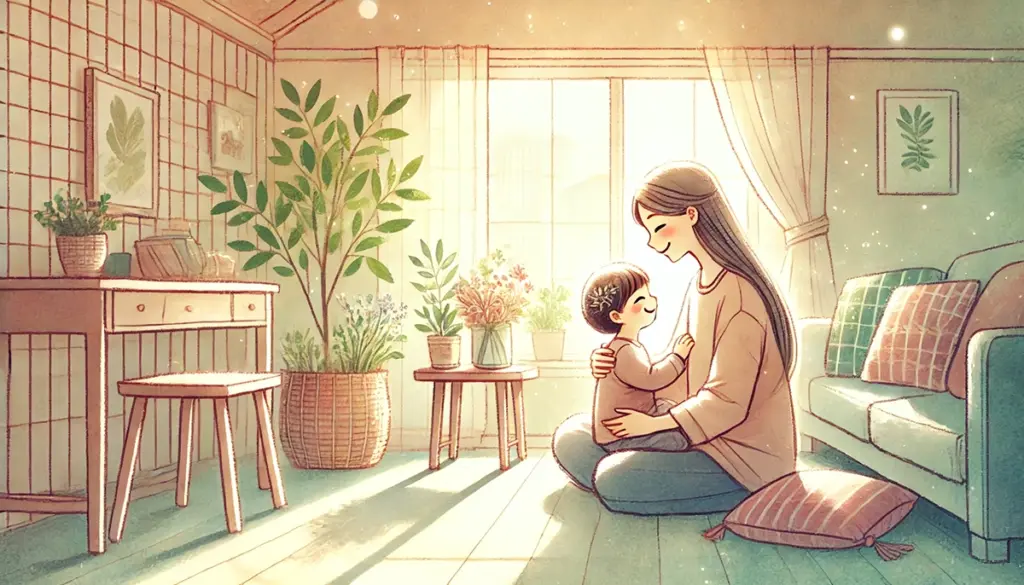
【参考文献】
- 村中直人(2023)『叱る依存が止まらない』
- Science誌掲載論文「Punishment and Reward System Activation」



