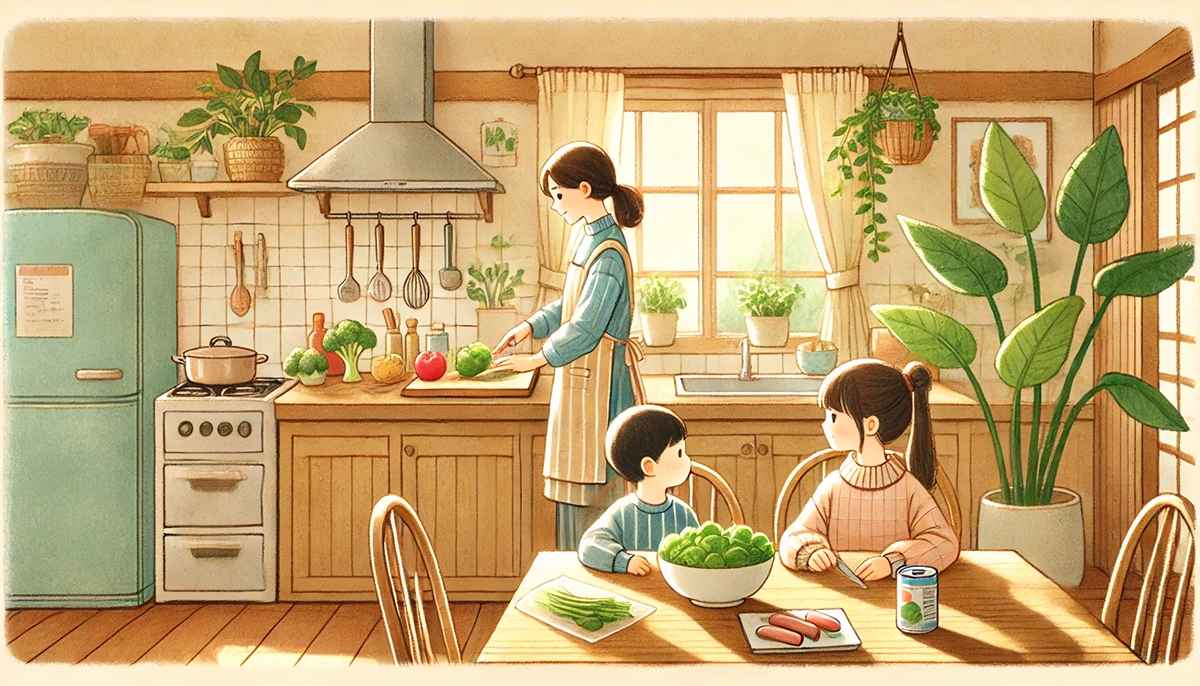毎日の歯みがき。「虫歯予防にはフッ素!」と思っていませんか?
でも最近、そのフッ素に思わぬリスクがあるかもしれないという話が注目されています。
この記事では、フッ素の意外な影響や、子どもの健康を守るためにママができることを、わかりやすく紹介します。
フッ素は体内で「フッ化水素」に変わる?
虫歯予防でよく使われるフッ化ナトリウム(NaF)。
水に溶けるとフッ素イオン(F⁻)になりますが、酸性条件下では「フッ化水素(HF)」という強い毒性を持つ物質に変化する可能性があります。
このフッ化水素は、
皮膚に触れると化学火傷 吸い込むと呼吸障害 体に入ると心臓や神経に悪影響
など、わずかな量でも深刻な影響を及ぼすことが知られています。
日本歯科新聞の記事とその反響 〜フッ素の安全性に関する懸念〜
2018年11月13日付の日本歯科新聞には、「フッ化ナトリウム(NaF)が体内でフッ化水素(HF)に変化する可能性がある」との記事が掲載されました。この記事は、歯みがき粉やフッ素洗口に使われるフッ化ナトリウムの安全性に対する新たな視点を提示したもので、医療現場や行政機関に波紋を広げました。
記事によると、フッ素の毒性の中心はフッ化水素であり、この物質が血液脳関門(BBB)を通過して脳に達する恐れがあると指摘されています。血液脳関門は通常、有害物質が脳に入らないように守ってくれる働きを持っていますが、それを越えて侵入する可能性があるというのです。
このような指摘を受け、子どもの脳や神経への影響を心配する声が一部の医療従事者や保護者から上がりました。特に、発達段階にある子どもへの長期的な影響については、注意が必要だという意見もあります。
さらに、フッ素は骨に蓄積されやすく、過剰摂取により骨フッ素症(骨の異常な硬化や痛み)や、歯の発達期における歯のフッ素症(白斑・着色など)を引き起こす可能性も指摘されています。
この報道に対して、2019年には日本口腔衛生学会が反論を発表しました。声明では、「フッ素は通常の使用濃度(歯みがき粉では1000ppm以下、洗口剤では500ppm以下)であれば、十分に安全性が確保されている」とし、フッ素の虫歯予防効果の重要性を強調しました。
しかしながら、「長期的な影響や子どもへの安全性に関しては、まだ不明な点も多く、今後の研究と情報開示が必要」という慎重な意見も依然として根強く存在しています。

アメリカでは10年以上前から議論されていた
アメリカでは10年以上前からフッ素の健康リスクが議論されており、一部の州では水道水へのフッ素添加を中止する動きが始まっています。妊婦のフッ素曝露と子どもの発達への影響(ADHDなど)を示唆する研究も複数あります。
ママにできることは?
子どもは大人よりも体が敏感。だからこそ、ママの選択がとても大切です。
歯みがき粉の成分表示をチェックしてみる フッ素無配合の製品を選ぶという選択肢もある 学校でのフッ素洗口について、事前に情報を確認する 代わりに、「分割ポリリン酸」などの安全性の高い成分が配合された歯みがき粉を選ぶのもおすすめです。ポリリン酸は、虫歯や歯の汚れ予防に役立ち、今のところ毒性や健康被害の報告は少なく、安心して使える成分として注目されています。
まとめ
フッ素には虫歯予防の効果がある一方で、体内で有害物質に変化するリスクがあるという新しい視点も必要です。
「毎日使うものだからこそ、安全なものを選びたい」。
ママのちょっとした気づきが、子どもの未来の健康を守る一歩になります。

【参考文献】
- 日本歯科新聞「フッ化ナトリウムは体内でフッ化水素に」(2018年11月13日号)
- 一般社団法人日本口腔衛生学会「報道に対する見解」(2019年8月18日 発表) 化学物質評価研究機構『フッ化水素酸に関する評価報告書』 MSDマニュアルプロフェッショナル版「フッ化水素酸曝露」
- 厚生労働省「職場のあんぜんサイト:フッ化水素の毒性情報」
- 羊土社『医学研究トリビア:フッ素ってやばいの?』(第28回)
- 小児歯科医ブログ「虫歯予防とフッ素をめぐる新しい動き」(2024年3月掲載)
- アメリカ環境保護庁(EPA)・疾病対策センター(CDC)の過去のフッ素政策報告