「人に迷惑をかけないようにしなさい」
そんなふうに子どもに声をかける場面、ありませんか?
もちろん、まわりへの配慮を伝えるのは大切なこと。
でも、もし子どもが「迷惑をかける=悪いこと」と思い込みすぎたら、誰かを頼ることや、間違えることさえ怖くなってしまうかもしれません。
今回は、インドに根付く考え方や、ガンジーの言葉をヒントに、「迷惑」に対する少し違った見方をご紹介します。
インドの教え:「人は誰かに迷惑をかけて生きている」
インドでは、子どもたちにこんなふうに教える学校もあります。
「人は誰かに迷惑をかけながら生きているもの。だから、人に迷惑をかけられたときには、許せる人になりなさい。」
この教えには、「誰でも不完全」という前提と、「だからこそ支え合おう」という温かい視点があります。
人と人との関係は、ミスや迷惑があっても、それを許し合うことで成り立つという考え方です。
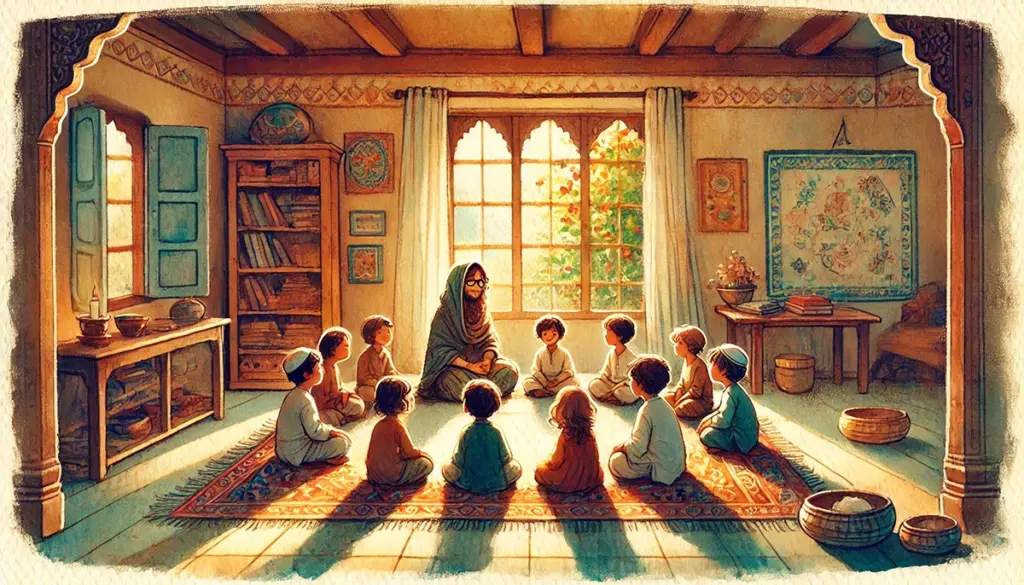
ガンジーの言葉:許すことは“強さ”の証
インドの偉人マハトマ・ガンジーは、こんな言葉を残しています。
「弱い者ほど相手を許すことができない。許すということは強さの証だ。」
許すという行為は、ただの我慢ではありません。
自分の感情をしっかり受け止めたうえで、相手の不完全さを受け入れることができる人こそが、本当に強い人だという教えです。
日本では「迷惑=悪」の意識が強い
一方、日本では「迷惑をかけないこと」が重視されます。
それ自体は悪くありませんが、強すぎると次のような傾向が生まれます。
- 他人のちょっとしたミスに厳しくなる
- 失敗や頼ることを恥ずかしいと感じる
- 誰かに助けられることを遠慮してしまう
そして、大人社会でもSNSでの誹謗中傷や「失敗を許さない空気」など、息苦しさにつながっている部分もあるかもしれません。
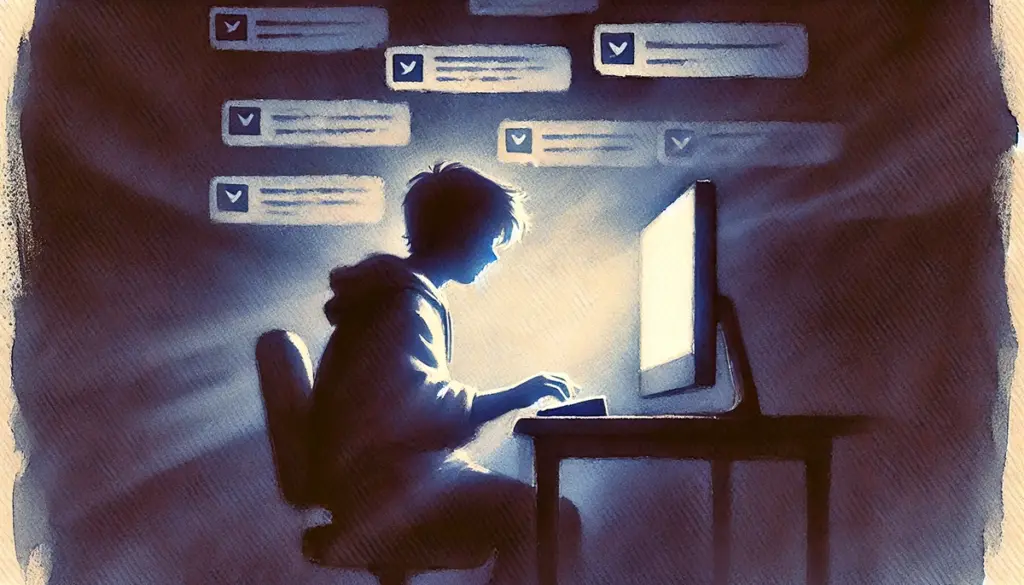
子どもには「許す力」も育てたい
子育てで大切なのは、「迷惑をかけない子」を育てることだけではありません。
「人はときに迷惑をかけたり、かけられたりしながら生きている」
「だからこそ、“ごめんね”と“いいよ”を言える関係を大切にしよう」
そんなふうに伝えていくことで、子どもは人の弱さも受け入れられる、やさしい心を持てるようになります。
さいごに|やさしさと強さはつながっている
「迷惑をかけないように」だけでなく、
「迷惑をかけても大丈夫。謝って、またやり直せばいい」
と伝えることで、子どもは安心し、のびのびと育っていけます。
そして、誰かの失敗に対しても、すぐに責めるのではなく、許せる強さを持った子に育ってくれたら――
それは、ガンジーが語った“本当の強さ”に近づいているのかもしれません。

【参考文献】
- 『子どもに伝えたいインドの教え』講談社(※教育現場での指導例を紹介)
- マハトマ・ガンジー名言集:「弱い者ほど相手を許すことができない。許すということは強さの証だ。」
- 『日本の道徳教育と社会的同調圧力』中山雅之(2020年、教育社会学研究)
- 総務省「インターネット利用環境実態調査」(令和5年度)



