ダイエットや健康の情報があふれる現代。
「高タンパクがいい」「糖質は減らすべき」「カロリーだけ気にすればOK」……。どれも一理あるようで、迷ってしまうことはありませんか?
そんな中で注目されているのが、日本人の体質に合った「少食」という選択肢です。
この「少食」は、単なる食事量の話ではありません。
ヨガやアーユルヴェーダといった東洋の智慧、そして最新の予防医学・遺伝子科学の観点からも、その価値が再確認されつつあるのです。
過剰なタンパク質が体に与える影響
現代の栄養指導に多い「高タンパク・低糖質」という考え方。
しかし杏林予防医学研究所の山田豊文先生は、これが西洋起源の栄養理論(フォイト栄養学)に偏っていると警鐘を鳴らします。
確かに、肉やチーズ、卵をしっかり食べる欧米人にとっては、高タンパクの食事はごく自然なもの。
アメリカ人などのように、代々肉食文化で生きてきた民族は、その食性に体が順応しています。
しかし、日本人は違います。
およそ1万年前から稲作文化を築き、主食は米、基本は野菜と豆、たまに魚。
菜食をベースとした民族として、胃腸のつくりもそれに合わせて進化してきたのです。
特に、日本人の腸は欧米人より長く、肉のような消化に時間がかかる食品を多く摂ると、
毒素が腸内に長くとどまってしまい、健康リスクが高まるとも言われています。
したがって、西洋の理論をそのまま取り入れるのではなく、
自分たちの民族的な体質に合った食べ方を見つめ直すことが、これからの健康のカギなのです。

「少食」で細胞が若返る?
科学が証明する“空腹の力”
1999年、マサチューセッツ工科大学のレオナルド・ガレンテ博士によって発見された「サーチュイン遺伝子(長寿遺伝子)」は、カロリー制限(空腹)によって活性化することがわかりました。
これにより、「少食長命」というヨガの教えが、医学的にも裏付けられたのです。
•1935年:コーネル大学のマッケイ博士は、「マウスに腹六分の食事を与えると寿命が2倍になる」と証明
•2009年:ウィスコンシン大学が行った実験で、腹七分のアカゲザルは、好きなだけ食べたサルより1.6倍長生きすることが確認
サーチュイン遺伝子が発動すると、細胞のDNAを保護し、老化の元である活性酸素などから守ってくれます。
また、消化吸収に使われるエネルギーが排毒(デトックス)に使われ、病気の原因となる“体毒”が流れやすくなるのです。
その結果、肌のハリも戻り、プロポーションも自然と整っていきます。
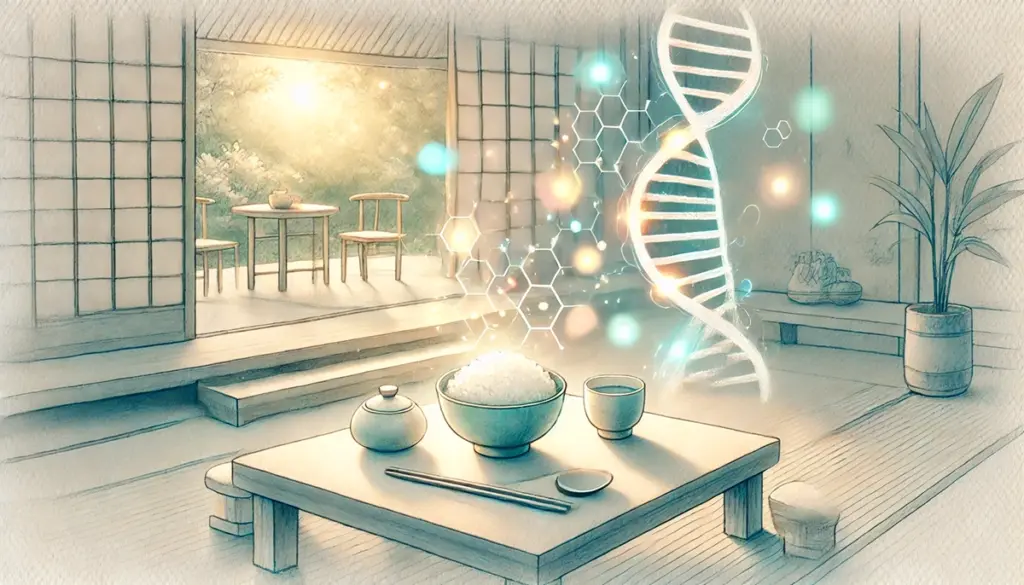
「食べすぎ」は老化と病気のもと ヨガが伝える“運命の食べる量”
ヨガには、次のような言葉があります:
「人は生まれたときに一生で食べる量が決まっている」
つまり、今たくさん食べれば、寿命を早く消費していることになるという考え方です。
この視点は、サーチュイン遺伝子のメカニズムとも重なります。
体にとっての「ごちそう」とは、むしろ“空腹”そのものなのかもしれません。
「1日3食」は本当に必要?
食とメディアに潜む“思い込み”
現代では、「1日3食しっかり食べること」が常識のようになっています。
しかしこの常識、実は教育やマスコミによって刷り込まれたものともいわれています。
フォイト栄養学を背景とした“カロリー至上主義”は、医療利権や食品業界の都合によって拡大されてきた側面があるのです。
本来、体の声に耳を傾けて必要な分だけ食べるのが自然なはず。
今こそ、私たちは“食べること”を見直す時期に来ているのではないでしょうか。
食を見直すことは、生き方を見直すこと
少食は「ガマン」ではなく、「自分を大切にするための選択肢」です。
日々の食事をほんの少し見直すだけで、体は軽くなり、心は静かになっていきます。
“足すこと”ではなく、“引くこと”。
それが、健やかで美しく歳を重ねる秘訣かもしれません。
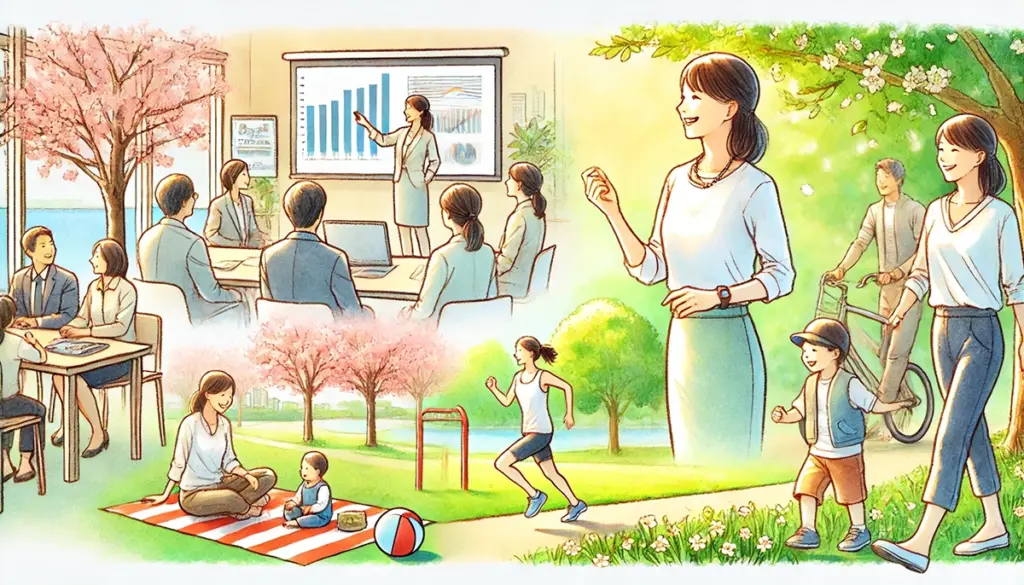
【参考文献】
- 山田豊文『食べない人はなぜ若い?』(青春出版社)
- 日本人の食と健康に関する栄養学的視点(厚生労働省)
- Leonard Guarente, MIT – Sirtuin Research (1999)
- Cornell University (1935), マッケイ博士によるカロリー制限実験
- University of Wisconsin (2009), アカゲザル長寿研究
- 『ヨーガ・スートラ』(パタンジャリ)
- 『アーユルヴェーダの智慧』(ヴァサント・ラッド)



